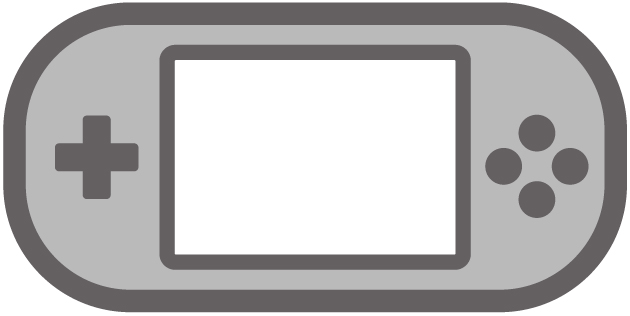※本記事は当事者が個人的にまとめた解説です。また、個人的な体験や感想であり、診断・治療を定めるものではありません。必要に応じて医師や専門家にご相談ください。診断や治療を決めるものではありません。
はじめに
私は小さい頃からテレビゲームが好きで、いろいろな機種で遊んできました。ところがある時期から、ゲームの途中で体調を崩すことが増えました。自分なりに振り返ると、原因の中心は画面から入ってくる情報量と映像の解像度(細かさ)ではないか——そう考えるようになりました。本記事は、私が何で疲れるのか、そしてどうすれば遊べるのかを、ASD当事者の視点でまとめたものです。
私が「疲れる瞬間」
- カメラの急旋回・視点の揺れ(カメラシェイク、モーションブラー、被写界深度の強調など)
- 画面全体が賑やか(光などのエフェクト・UI通知・ミニマップなどが同時に点灯)
- 高解像度で細部がギラつく(精細さはきれいだが、細かいチラつきで目が疲れる)
- マルチの同時要求(敵の動き、味方の位置、チャット、スキル回しなどを一度に追う)
まとめると、視覚と聴覚の入力が多いほど、そして同時に処理することが増えるほど、私は疲れやすいようです。
なぜ負荷になるのか(私の仮説)
- 視覚の入力が強すぎる:高解像度・高コントラスト・高輝度は細部まで目に入る一方、不要な刺激を遮るのにエネルギーが要る。
- 流れが速い:急なカメラ移動や画面全体の動きは、目と体の感覚のズレを生み、酔いやすさや疲れにつながる。
- 情報の“重なり”:通知などが多いと、どれが重要かを選び分ける作業が増える。
疲労サイン(私のチェックリスト)
- 文字列が読み返しになり始める
- 目の奥が熱い/痛い/ピリピリする
- 呼吸が浅い、肩が上がっている
- ため息やイラつきが増える
- 立ち上がったときにふらつく
→ 2つ以上出たらいったん中断。水分、深呼吸、遠くを見る。
すぐできる「設定」の調整
映像
- カメラ揺れ/画面のブレ/モーションブラー:OFF
- いろいろな画面の設定:OFFまたは弱
- 粒子・エフェクト密度:低〜中
- フレームレート優先モード(ヌルヌル動く方が目が楽なことが多いかも)
- 画面の明るさ・コントラスト:部屋の照明に合わせてやや低め
- FOV(視野角):広すぎても狭すぎても酔うことがあるので、自分に合う方へ微調整
- 解像度・アンチエイリアス:ジャギー(ギザギザ)やチラつきが減る設定に
UI(HUD)
- HUDのスケールを小さく/必要ない表示をOFF
- 字幕ON(聴覚の負荷を下げる場合は有効かも)
音・振動
- マスターボリュームを気持ち下げる
- ダイナミックレンジを使い、急な大音量を抑える
- コントローラの振動などはOFF(私はOFF)
プレイのやり方(私に効いたこと)
- プレイ時間は短め×区切る:25〜40分遊んだら5〜10分休む(席を立ち、遠くを見る/水分補給)
- カメラ感度を下げる:急旋回を減らす
- やることを減らす:ゲーム内で疲れそうなミニゲームなどがあるとき、その部分をなるべく避けたり、無理に長時間遊ばない
- 目のケア:瞬きを意識する
- 距離と姿勢:画面との距離をやや遠めに、背中と首に負担がかからない椅子にする
ゲーム選びの指針(個人差あり)
- 疲れにくいことが多い:古いゲーム・2Dグラフィック・ターン制RPGなど
- 体調の良い日に短時間:演出が派手なゲーム・構築する要素(頭を使い、かつ画面の文字に集中するデッキの構築などのこと)・3DのFPS/TPS/アクションなど
- “一時停止が効く”ゲーム:休憩しやすく、遊びやすい
- YouTubeなど動画+攻略サイト+ゲーム画面などを同時に開かない: マルチタスクは疲れやすい
まとめ
私は、情報量と解像度の高さが心地よさと引き換えに負荷にもなり得ると実感しています。
映像・音などの設定、短時間+休憩、このあたりを整えるだけで、「遊べる時間」と「遊んだ後の回復の早さ」ははっきり変わりました。
ゲームは本来、楽しい時間のはずです。体調と相談しながら、自分に合う遊び方を見つけていきましょう。