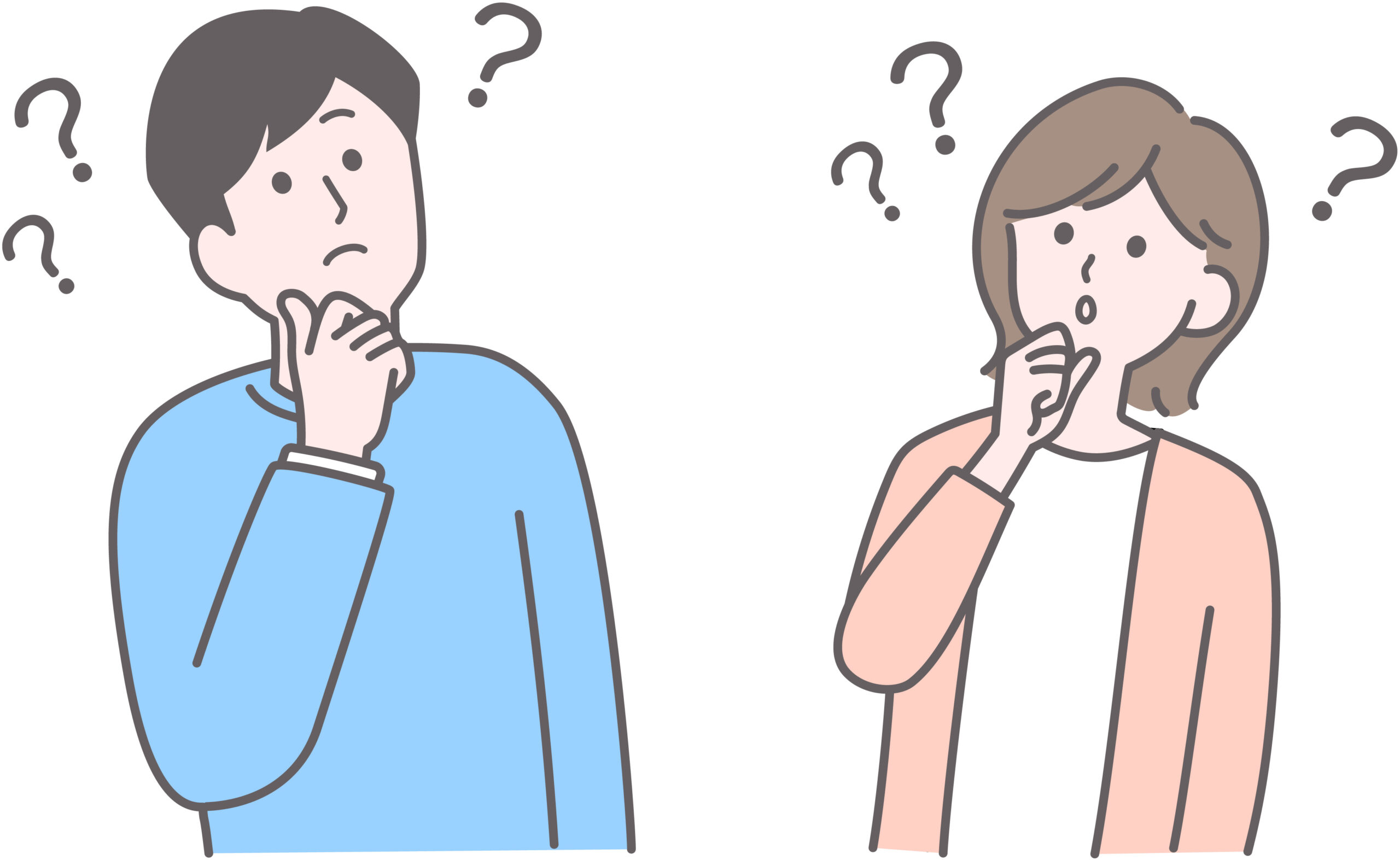※当事者の体験と学びをベースにした一般向けのまとめです。医学的診断を定めるものではありません。気になる症状がある場合は専門家へ。
はじめに
ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)は併存することがあり、見た目の共通点も多く、本人も周囲も混乱しがちです。
私自身はASDが主ですが、ADHD併存の診断も受けています。
これまで「ミスが出る」「集中しづらい」「先延ばしにしてしまう」「会話で衝動的に発言してしまう」といった困りの原因がASD由来なのかADHD由来なのか、長く見分けがつきませんでした。
ただ、自分の状態を丁寧に観察していくと、同じ“不注意”でも背景の理由が異なることがあり、また歩き回るような多動は私には見られない、など特徴の出方に差があることがわかってきました。
本記事では、当事者の視点から「重なりやすいところ」と「分かれ目になりやすいところ」を整理していきます。診断を定める目的ではなく、日常の理解の手助けとしてお読みください。
共通して起きやすいこと
ASDとADHDでは、見た目が似た困りごとがしばしば起こります。
ただし、背景の理由が異なることがあります。
- マルチタスクでのミス
- ASDの背景:同時に複数の情報を保持・統合することが負担になり、取りこぼしが出やすい。
- ADHDの背景:注意の維持・切替・抑制が揺らぎ、作業途中で別の刺激に引っ張られやすい。
- 時間管理(タスクの見積もり・順序づけ)
- ASDの背景:急な変更や並列な進行で混乱しやすいが、順番を決めれば進みやすい。
- ADHDの背景:着手までが遠い/先延ばしになりやすい。短い締切や小さな区切りがないと動きにくい。
- 対人コミュニケーションの行き違い
- ASDの背景:暗黙の合図や文脈の切り替えを捉えにくい。
- ADHDの背景:相手の発話を最後まで待てずに割り込む・話題が逸れやすい。
- 集中の途切れ/疲れやすさ
- ASDの背景:音・光・人の動きなど入力が多すぎると消耗しやすい。
- ADHDの背景:退屈に耐えにくく、覚醒の弱さや刺激への欲求で集中が波打ちやすい。
これらはASDやADHDに限らず、睡眠不足・不安やストレス・身体コンディション・環境要因などでも起こり得ます。状況と背景を分けて見ることが役立ちます。
注意の維持について
- ASD寄り:
- 興味がある領域では深く集中できるが、不要な刺激の遮断に苦労する。
- 情報の粒が立って入る(音・光・文字の乱れなど)ため、整理に時間がかかる。
- ADHD寄り:
- 注意の維持・切替・抑制が不安定。退屈に耐えにくく、着手までが遠い。
- 外部刺激に引っ張られやすい/衝動的に手が動くことがある。
見極めメモ
- 「始めるまでが遠い」「締切直前だけ火がつく」→ADHD寄りのサインになりやすい。
- 「ノイズによる疲弊がある」「一度に複数のことを行うと崩れる」→ASD寄りのサインになりやすい。
コミュニケーションの違い
- ASD:暗黙の前提/合図を拾いにくい
- ADHD:話題の逸脱や割り込み、最後まで聞く前に反応してしまう…といった抑制の難しさが目立ちやすい。
時間感覚と段取り
- ASD:順番に置けば進む。逆に、同時処理や急な変更でフリーズ。
- ADHD:始めるために「点火」が要る。点火すれば一気に進むが、持続に波がある。
まとめ
- 見た目は似ても、背景は違うことが多い。
- 注意の維持
ASD寄り:音・光・人の動きなどで疲れやすい。
ADHD寄り:退屈だと動き出しにくく、締切前に一気に進みがち。
- コミュニケーション
ASD寄り:暗黙の合図や文脈の切り替えが取りにくい。
ADHD寄り:割り込みや話題の逸脱など、抑制の難しさが目立つ。
- 時間感覚と段取り
ASD寄り:逐次的に処理をする場合は順調に進むが、並列な進行や急な変更でつまずきやすい。
ADHD寄り:着手のきっかけ(点火)と短い区切りがあると進みやすい。
気になる状態が続く場合は、医療機関や支援機関に相談してください。