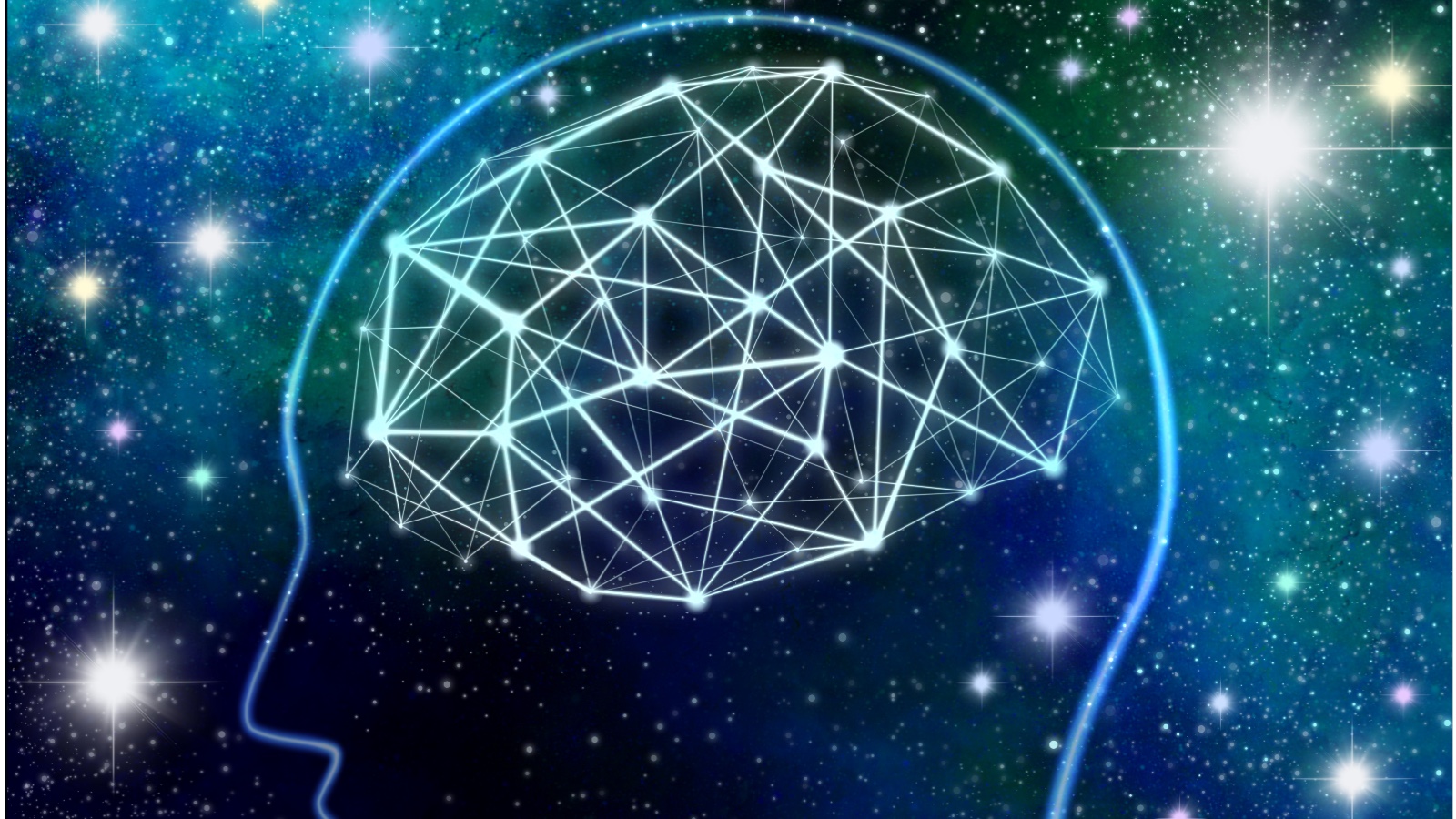※本記事は当事者が個人的にまとめた解説です。また、個人的な体験や感想であり、診断・治療を定めるものではありません。必要に応じて医師や専門家にご相談ください。診断や治療を決めるものではありません。
はじめに
ハイパーファンタジアとは、頭の中の映像がとても鮮明で、知覚に近いレベルで見える状態を指します。
反対に、映像が浮かばなかったり、ほとんど浮かばない/極端に不鮮明な状態はアファンタジアと呼ばれます。どちらも疾患名ではなく、心的イメージの個性です。
定義とスペクトラム
- ハイパーファンタジア:頭の中で描く映像が知覚に近い鮮明さをもつ。色、陰影、質感、動きまで再現されることがある。
- アファンタジア:自発的な視覚イメージが極端に弱い、あるいは生じにくい。会話の中で初めて、「他の人は言語だけで考えているわけではない」と気づくこともある。
- 心的イメージは0か1かではなく、連続体(スペクトラム)として捉えられ、両端にハイパーファンタジアとアファンタジアが位置付けられる。
どう測る?(主観 × 客観)
1) 映像を浮かべて自己申告する(VVIQ)
「友人の顔」「店先」「山と湖」などの場面を鮮明さで評価する標準質問紙 VVIQ を用います。
代表的な5段階の記述は以下です(点数の向きは場合により逆になることがあります)。
- 実際に見ているのと同じくらい鮮明
- かなり鮮明
- 中くらいに鮮明
- ぼんやりしている/薄い
- まったく像が浮かばない(考えていることは分かる)
2) 瞳孔反応を客観的にみる
明るいものを想像すると、実際に明るいものを見たときと同様に瞳孔が縮むことがあります。
アファンタジア群ではこの“想像由来の縮瞳”が著しく弱いことが報告され、生理学的な指標として用いられます。
3) 両眼視野闘争のプライミング
左右の目に異なる像を同時提示すると、どちらが先に見えるか“競合”が起こります。
直前に頭の中で描いた像が知覚の勝ちやすさを上げることがあり、イメージの強さの行動学的指標として使われます。
ポイント:主観(VVIQ)+客観(瞳孔・視野闘争)の二本柱により、「自己申告だけではない」説明が可能です。
脳と認知の違い(要点)
- ネットワーク仮説:前頭前野と視覚皮質の機能結合が関与し、ハイパーファンタジアでは内側から視覚系を起動しやすい可能性が示唆されています。
- 記憶・未来思考:自伝的記憶の臨場感、将来の場面のシミュレーションの豊かさなどに群差が観察されます。
- 夢:覚醒時イメージと夢の鮮明さは部分的に独立しており、アファンタジアでも視覚夢をみる人は少なくありません。
ASDとの関係(未解明)
重要:ASD=視覚イメージが必ず強いわけではありません。ASD内部にもアファンタジア〜ハイパーファンタジアまで幅広く分布します。アファンタジアと自閉傾向の関連を示す報告もありますが、臨床診断ASDでの直接検証は限定的で、個人差が大きい前提で読むのが安全です。
「カメラアイ」との線引き
ハイパーファンタジアは「いま想像する像の鮮明さ」の話です。
過去の体験を写真のように完全コピーして思い出す、いわゆる「カメラアイ」(フォトグラフィックメモリ)とは別領域です。
まとめ
- ハイパーファンタジアは、想像したイメージが非常に鮮明
- アファンタジアは、イメージが浮かびにくく、思考は言語に依拠しやすい
- アファンタジアと自閉傾向の関連を示す報告もあるが個人差も大きい